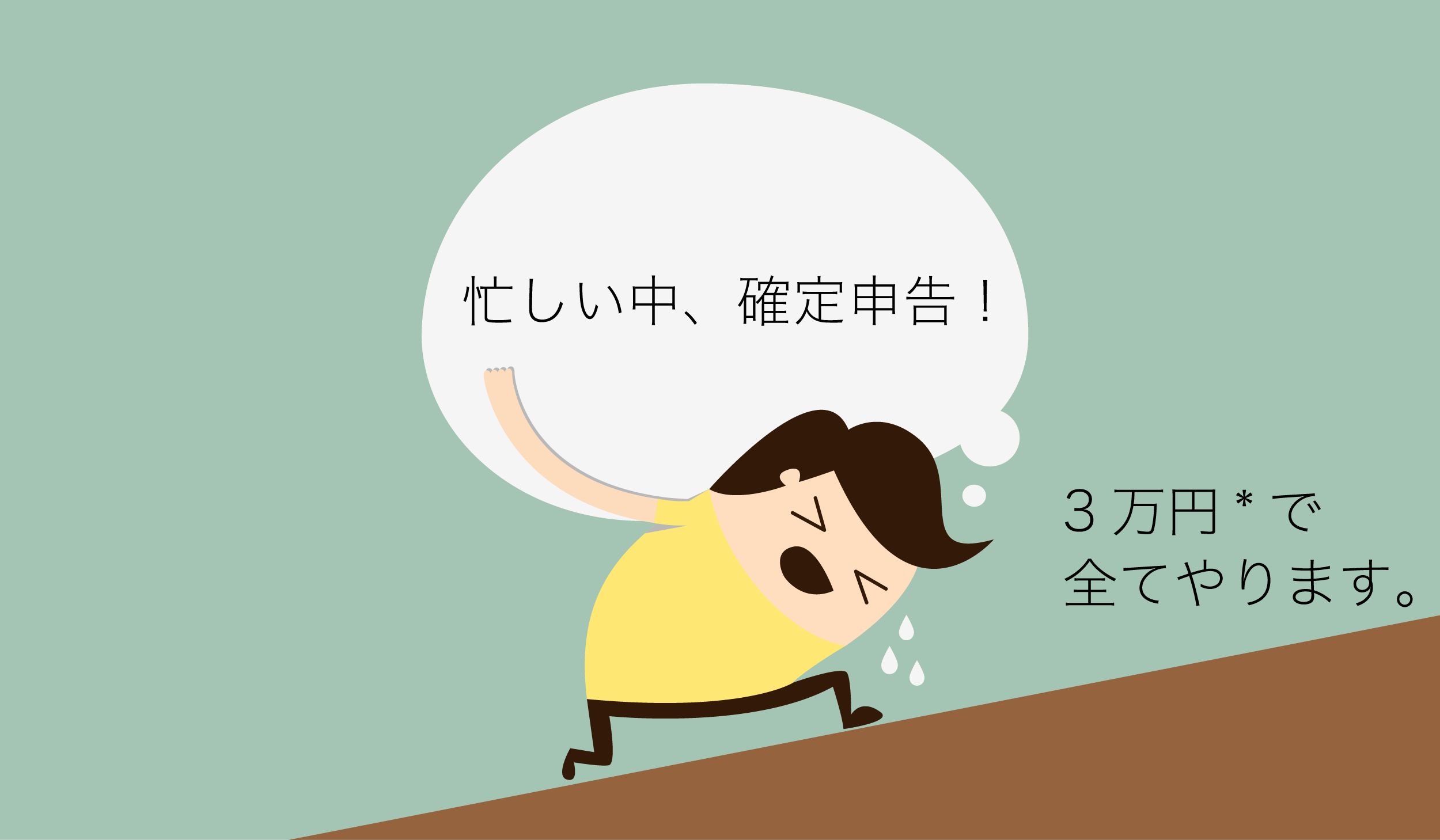MENU
確定申告の申告方法と期限
確定申告の項目
Ⅰ 申告書作成前にすること
- 必要書類を準備しておきます
- 所得の種類や控除の内容によっては、必要書類が異なりますが、日頃から領収書や証明書類などは整理しておくと、確定申告の作成の際あわてなくて済みます。
- 例:源泉徴収票、支払調書、領収書(必要経費になるもの、医療費、国民健康保険、国民年金、寄付金)、証明書(借入金の年末残高等証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書)等
- 申告用紙を入手します
Ⅱ 申告用紙の入手方法
- ①税務署でもらうことができます
- (1月半ばに税務署に置かれます。平日は8時半より17時まで開いています。一部の税務署では、確定申告期間中、日曜日も相談受付しているところがあるようなので、詳細につきましては、国税庁のホームページ又は、管轄の税務署へお問い合わせください。)
- ②国税庁のホームページからダウンロードできます
- 申告内容によっては、必要な書類が異なりますので注意してください。
- ③税務署から申告書や納付書が送られてくることがあります
- 前年に確定申告をし、申告書の「翌年以降送付不要」に○をしていない場合には、送られてきます。○をしている場合で、納付の方法を振替納税やダイレクト納税にしていない場合には、納付書のみ送られてくる場合があります。
Ⅲ 必要な確定申告書
- ①申告書A 第一表、第二表
- (所得の種類が、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額がない場合に使うことができます。申告書Bに比べて簡素化されています。
- ②申告書B 第一表、第二表
- すべての所得で使うことができます。予定納税額のある場合にはこちらの申告書を使います。
- ③申告書(分離課税用) 第三表
- 土地・建物、株などの譲渡所得、退職所得、山林所得、先物取引の雑所得のいずれかがある場合には、申告書Bに加えて必要になります。
- ④申告書(損失申告用) 第四表
- 今年の所得金額が赤字、またその年の所得金額から損失金額を引ききれない場合には、申告書Bに加えて必要になります。
- ⑤特別な計算書類 例)
- ・住宅ローン控除を受ける場合・・・申告書A又はBに加えて「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が必要になります。
- ・自宅を売却した利益を申告する場合・・・申告書B、及び申告書(分離課税用)に加えて「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」が必要になります。
- ・株を売却した利益を申告する場合・・・申告書B、及び申告書(分離課税用)に加えて「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」が必要になります。
- ・医療費控除を受ける場合・・・申告書A又Bに加えて「医療費の明細書」が必要になります。
- ・個人事業主、フリーランスの場合・・・申告書Bに加えて「収支内訳書」(青色申告を行う場合には、「青色申告決算書」)が必要になります。
Ⅳ 申告書の作成
- 自分で作成する
- 税務署で「所得税の確定申告書の手引き」を用意していますので、こちらを参考に作成を進める方法、また申告相談や相談会場を設けている場合もありますので、税務書へ行って申告書作成をする方法、国税庁ホームページには「確定申告書等作成コーナー」があり、案内にそって金額等を入力し、申告書を作成することもできます。
- 税理士に依頼する
- お金はかかってしまいますが、必要な書類を用意すれば税金を正確に計算、アドバイスをしてくれるので、依頼することも有効な方法です。
Ⅴ 税務署への申告方法と期限
- ① 紙申告
- 紙の用紙に必要事項を記入、記名・押印し申告書等を提出します。管轄の税務署へ持参し提出、郵送でも提出できます。
- ② 電子申告
- 紙ではなく、申告書データを電子送信し申告する方法です。押印する必要はなくなります。添付書類が省略できるものがあります。自分で作成し送信する場合には、事前準備が必要です(利用環境確認、電子証明書の取得、ICカードリーダライタの準備)。税理士に依頼する場合には、事前準備は不要です。
- 確定申告受付期間
- 2月16日から3月15日(土日の関係で年によって変動します)。
リクルート

当法人では業務拡大により職員を募集しています。資格取得を考えている方もぜひ。
税理士荒井正巳ブログ

自身も経営者であり、経営者の目線で当法人や税務にまつわることを書いていきます。ときどき、山のことも。
スタッフブログ

約40名のスタッフ全員参加のブログです。税務の最新情報や日々の出来事を、分かりやすく書いています。
代表税理士 荒井の考え

お客様と共に成長し続ける会計事務所でありたいと考えています。お客様の成長のお手伝いをし、当法人も成長していくことを使命としています。
会社設立相談も無料です

長年会社設立とその後の経営業務に携わってきた専任スタッフがマンツーマンで対応します。会社設立は設立後が大事です。
専任の社会保険労務士

法人内に社労士(社会保険労務士 三枝孝裕)が常駐。助成金申請や就業規則等を会計とワンストップでスピーディに対応します。
税理士等が対応します
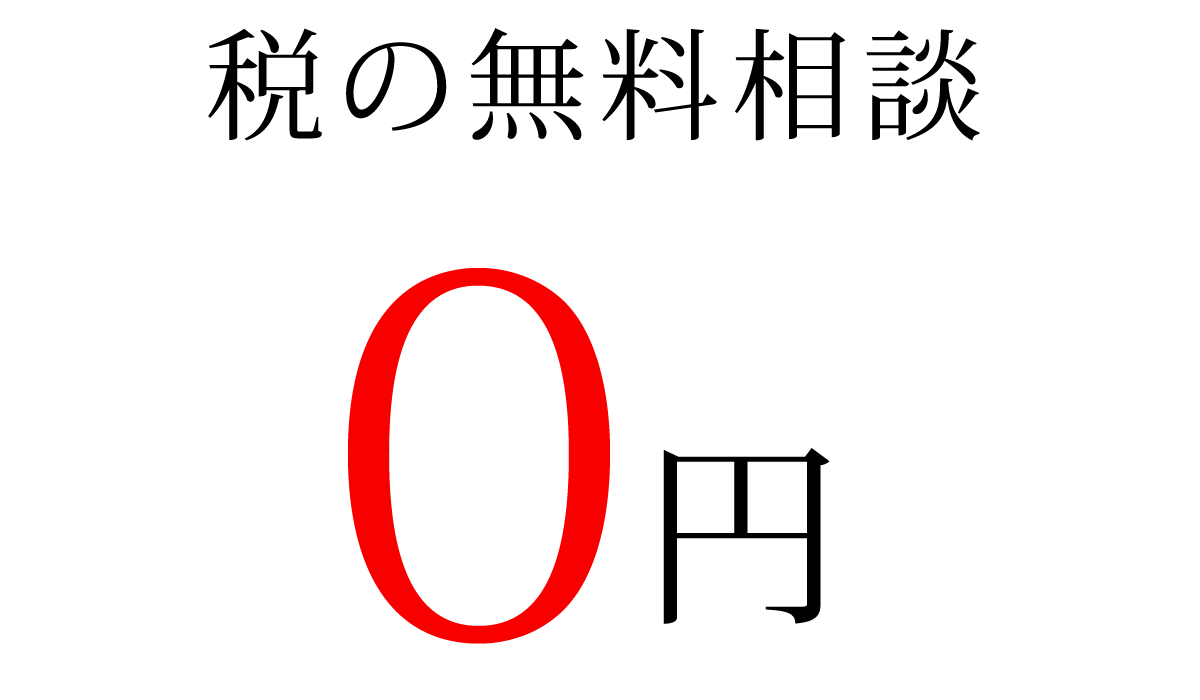
無料でも本格的にご対応します。相続・遺言等のご相談も承ります。お電話でもご来社でも1時間までご相談無料です。(豊島区及び近隣の方限定)
法人成りをお考えなら
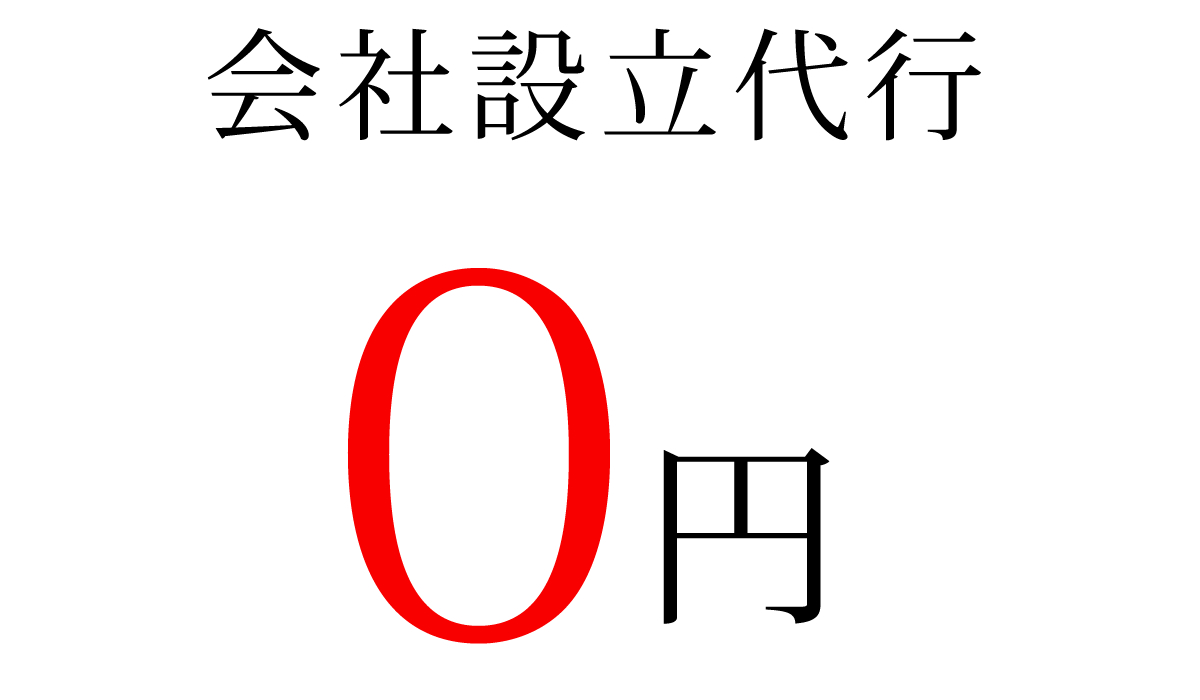
最初だけ安くても意味がありません。会社設立後も、当法人なら専任社労士と提携し会計・就労業務をワンストップで無駄なく行います。
創業融資サポート

日本政策金融公庫の都内の支店には当法人の担当者がいます。当法人なら、公庫を納得させる「創業計画書」作成・提出の全面サポートが可能です。